「無理」というのは簡単、でもそれでいいんですか?
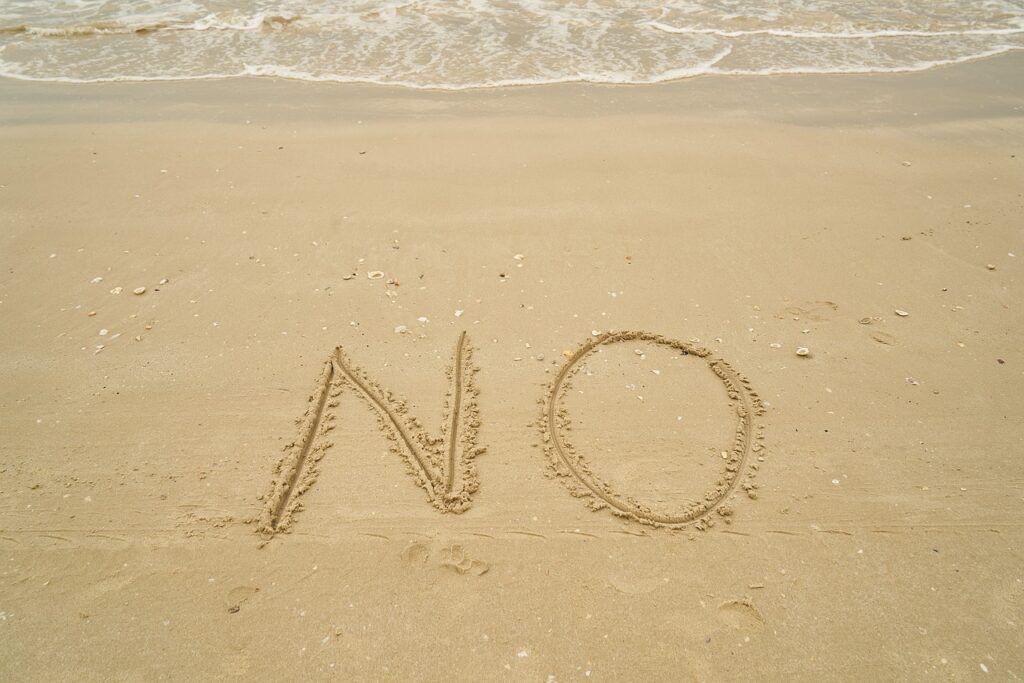
目次
なぜ私たちは「無理」と言ってしまうのか
「それ、無理です」
ビジネスの現場で、こんな言葉を耳にすることは少なくありません。売上の目標、納期の短縮、新規市場への進出……プレッシャーの強い環境では、やる前から「無理」と思ってしまうこともあるでしょう。
むしろ、それが合理的で現実的な判断だと感じることさえあります。
しかし、「無理」という言葉には、私たちの行動を止めてしまう力があります。
それは自分の手を動かす前に、思考も選択肢も閉ざしてしまうブレーキのようなものです。では、その「無理」は本当に事実なのでしょうか? それとも、自分自身の内面から湧き出した“感情”や“思い込み”なのでしょうか?
この問いを持つことこそが、変化と成長への第一歩になります。
「無理」は思考の停止であり、責任の放棄である
「無理」と言うとき、私たちはたいてい「私の責任ではない」「これは私の手には負えない」といった思考を心のどこかで抱えているのではありませんか。たとえば、上司から新たな目標を提示されたときに、「そんなの現場を知らないから言えることだ」と返す部下がいるとします。
このとき本当に問われているのは、「それができるかどうか」ではなく、「あなたはそこに責任を持って向き合う意思があるかどうか」だとしたら。
確かに「無理」と言ってしまえば、その責任から一歩引くことができます。たとえ、上司からの命令で引き受けるにしても、上司や環境のせいにすることで、自分が動かなくても済むか、又は「自分の責任ではない」という“安心”を得られます。けれどそれは、可能性の芽を自ら摘み取る行為でもあるように思います。
「無理」と感じる自分の内面を探ってみる
「無理だ」と感じるとき、私たちの心の中では何が起きているのでしょうか?
大切なのは、その感情の正体を見つめることです。
• 恐れ1:失敗して評価を落とすこと
「もしチャレンジして失敗したら、上司や同僚からどう思われるだろう」
これは多くのビジネスパーソンが抱く不安です。成果主義の文化では、失敗は避けたいものです。しかし失敗を恐れるあまり挑戦を避けると、長期的には成長の機会を失ってしまいます。
• 恐れ2:自分の限界を認めること
「これは自分には無理だ」と感じるとき、その奥には「できなかった自分」を直視する恐れがあることも。
人は誰でも、自分に期待していたいものです。しかし現実がその期待に届かないとき、無力感や羞恥心が生まれます。それを避けるために、「最初からやらなかった」と言える状況に逃げることもあるのです。
• 恐れ3:孤独な責任を負うこと
特にリーダーや中間管理職に多いのが、「自分だけが背負わされるのではないか」という不安です。誰にも相談できず、成果だけを求められる環境では、「無理」と言いたくなるのも当然かもしれません。
けれど、そうした感情を見つめ、「なぜ自分は無理だと思っているのか?」と内省することで、現実の打開策が見えてくることがあります。
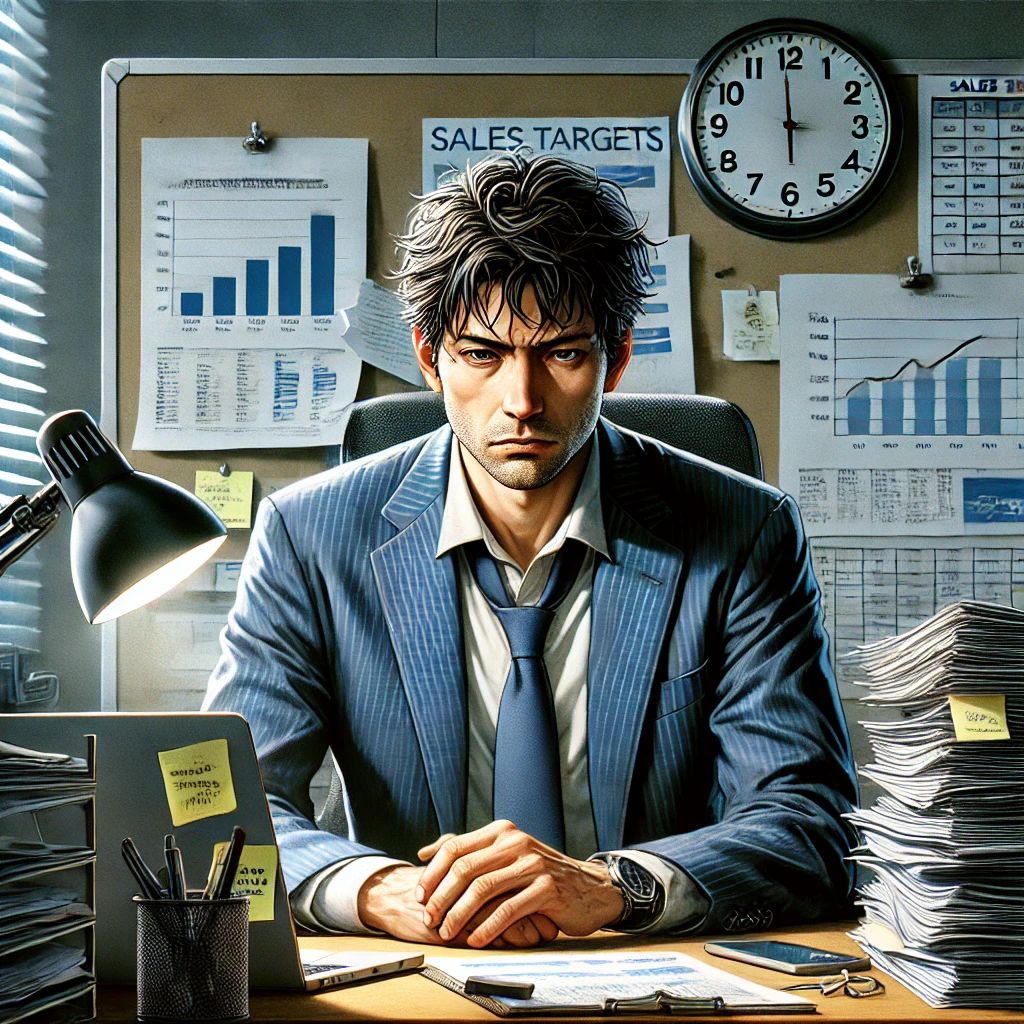
事例を通して知る「無理」との向き合い方
川島翔太(仮名)は、30代前半の若手リーダー。中堅メーカーの営業部門で、既存顧客の売上確保と、新規市場への拡販の両方を任されていました。上司からは「来期は既存売上を落とさずに、新市場で5%の売上を作れ」との指示。しかし、チームの人員は増員されることもなく、部下は日々のルーティン業務で手一杯です。
「無理だ……」
川島は最初、心の中でそうつぶやきました。
既存顧客の関係性は繊細で、少しでも対応が遅れれば信頼を失う。新規市場へのアプローチは時間も労力もかかる。それを両立させる人材も時間もない。上司は現場を知らず、無責任な目標を掲げている──そう思いました。
しかしある日、ふと自問します。
「これは本当に無理なのか? それとも、自分が“無理だと思いたい”だけではないのか?」
その問いが、川島の思考を変え始めました。彼は「できない理由」を並べるのをやめ、「できること」から始めると決めました。まずは既存顧客対応を効率化するためのフォーマットを部下と共に見直し、週に2時間だけでも新規開拓に集中できる時間を捻出。
さらに、若手社員に新市場の情報収集を任せることで、巻き込みと育成を両立させました。完璧ではないにせよ、「完全に無理ではない」という実感が、行動を生み出していったのです。
結果として、新市場での売上はわずか2%増にとどまりましたが、川島は部長から「確実に道を作った」と評価され、次の期では支援体制の拡充も決定。川島自身、「“無理”と決めつけていたのは自分の心だった」と語ります。この物語は、実際の事例からつくり上げたフィクションですが、「無理」に対してどう向き合うかを示したものです。
無理から可能へ──行動につなげる3ステップ
川島のように「無理」を乗り越えるには、内面と向き合った上で具体的な行動に移す必要があります。以下の3ステップが、その突破口となるでしょう。
ステップ1:課題を小さく分解する
「新市場での売上5%増」ではなく、「週に2件の新規訪問」「既存対応を10%効率化」など、行動に落とし込める単位にまで分けて考える。
ステップ2:感情と事実を分ける
「怖い」「責任が重い」という感情と、「本当に時間が足りない」「リソースが不足している」という事実を区別して整理する。
ステップ3:巻き込み・相談のアクションを起こす
一人で抱え込まず、部下・同僚・他部署の知恵を借りる。協力を求めることは、弱さではなくリーダーシップの一部である。
まとめ:「無理」の正体に気づいた先にあるもの
「無理」という言葉は、ときに正しい判断を助けることもあります。しかし、その言葉を使う前に、自分が何を恐れ、どこで責任から距離を取ろうとしているのかに気づくことは、とても重要です。
行動を止めるのではなく、内面を探り、「では何ができるか?」を問い直す。
その小さな一歩が、ビジネスの未来を変えていきます。あなたが「無理」と思っているその課題も、ほんの少し見方を変えるだけで、動き出す可能性を秘めています。
「無理」と思うことを、100%無くそうという事ではありません。「無理」と考える前に、できる前提を持って、方法を考えてみる。
特に、自分たちの未来に向かって進む過程での、困難には、できる前提で進みたいと思います。


